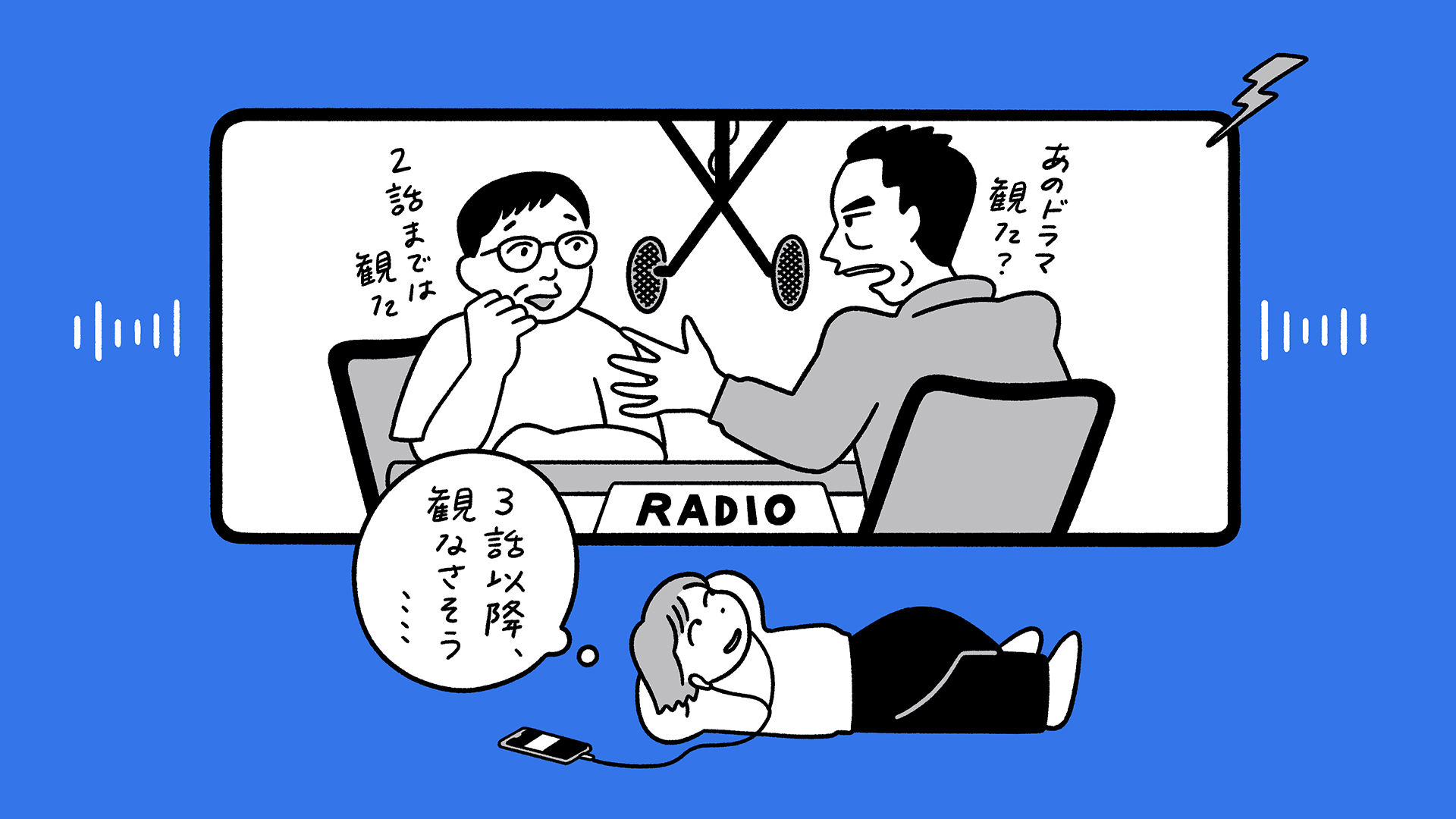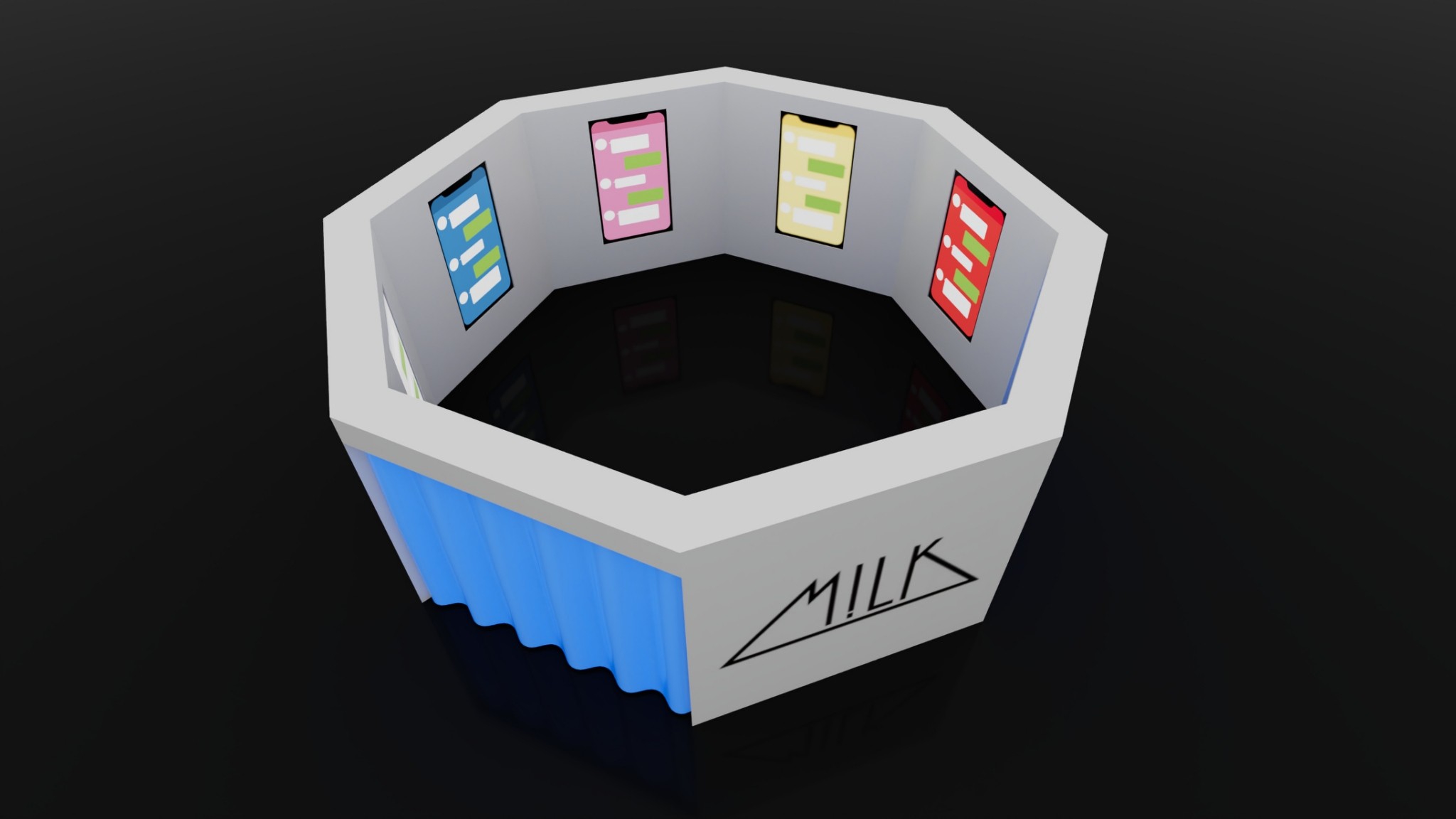クィアなわたしとドラゴンボールの摩訶不思議アドベンチャー | 中里虎鉄
2024年3月8日、世界中、もしかしたら宇宙の誰もが知る偉大な漫画家、鳥山明氏の訃報が知らされた。その日、わたしが『ドラゴンボール』好きだということを知っている友人からメッセージが届き、その数秒後にニュースアプリの速報でわたしは鳥山氏の死去を知った。
これまでに数多くの名作を世に残し、世代、性別、人種を超えて、わたしたちに笑いと感動、そして成長することの喜びを届けてきた鳥山氏。今年の秋からは、『ドラゴンボール』の完全オリジナル新作アニメが放送予定だったこともあり、鳥山明伝説はまだまだ続いていくと思われた矢先だったため、突然の訃報に多くの人がショックを受けたことだろう。わたしもそのうちの1人だ。多くの人がSNSを通して、自分と鳥山明作品(特に『ドラゴンボール』)との思い出を発信する姿を見て、彼の作品がどれだけの人に愛され、どれだけの人とともに成長してきたのかを改めて知ることになった。
わたしとしても、個人的な『ドラゴンボール』との思い出を語りたくても、どこで話したらいいんだろうと悶々としていたところ、今回のコラム執筆の依頼を受け(ホンットありがたい…)、時間をかけてわたしと『ドラゴンボール』の関係性や思い出を振り返ることにした。この記事は『ドラゴンボール』の魅力を語るものではなく、わたし個人と『ドラゴンボール』の関係性についての話。

安心材料として選択した『ドラゴンボール』
そもそもわたしはノンバイナリー(わたしの場合は、男性でも女性でもない性自認)を自認している。幼少期や10代の頃は、自分の性のあり方に名前があることも知らなかったから、自分のことはゲイの男の子だと思っていた(もちろん、そう自認するまでにも時間はかかったが)。小さい頃は可愛いものやフェミニンなものが好きで、いつも姉が持っていた『カードキャプターさくら』のステッキや『おジャ魔女どれみ』の変身アイテムに魅力を感じながらも、クリスマスプレゼントとして親から与えられた『仮面ライダークウガ』の剣で遊んでいた。「姉とケンカするうえでは、この剣の方が強いか」と自分に言い聞かせ、喜んでいる素ぶりを見せていたが、本心は「これじゃない」と思い続けていた。
そんなわたしが6歳の頃に、祖父母を訪ねて姉と鹿児島に行ったとき、祖母に「なんでも好きなマンガを買ってあげる」と言われ、本屋に連れて行ってもらったことがある。わたし自身は貧困家庭に育っていることもあり、マンガを買ってもらったことはなく、唯一与えられていたエンタメは、共働きの親が不在時に楽しめるようにと契約したケーブルテレビだった。『キッズステーション』と『カートゥーンネットワーク』で再放送していたアニメを見ていたわたしと姉は、自然と本屋さんでも知っているアニメの原作を手に取った。姉が選んだのは母の好きな高橋留美子氏の『らんま1/2』、そしてわたしが選んだのは『ドラゴンボール』だった。きっと当時のわたしは、何が“男の子用”で何が“女の子用”なのかを理解し、わたしが観ていると親が喜んだ『ドラゴンボール』を選んだのだろう。正直、それまでは『ドラゴンボール』も観ているフリをしていただけだから、実質わたしと『ドラゴンボール』の出会いはこのときだった。
“普通の男の子”として見てもらえる切符のようなもの
初めはそこまで興味を持って読んでいたわけではないが、次第に無邪気でわんぱくだけど、心優しい主人公の孫悟空に惹かれ、彼がどんな試練も仲間とともに乗り越えていくストーリーに熱中していった。正直、わたしの初恋は孫悟空だったのかもしれない。二次元であれば、「悟空が好き!」と言っても、ある種「男としての憧れ」に集約できたし、多くの少年たちが好きなキャラクターだったから、わたしがシスヘテロの男の子としてカモフラージュをすることもできたのだ。当時のわたしにとっては、誰からも勘ぐられずに恋心を抱ける救いの世界だったのかもしれない。
そんな世界に没入したわたしは、マンガを何度も読み返し、アニメを何度も見返し、マンガでは描かれなかった『ドラゴンボールZ』の続編となるアニメオリジナルシリーズ『ドラゴンボールGT』に心を踊らせ、誕生日やクリスマスのプレゼントに『ドラゴンボール』のCDや公式ガイドブックなどのグッズを揃えていった。そうしたわたしの行動は、親を、周囲を“安心”させる材料にもなっていた。幼い頃から好きな物事も言動も「おかまちゃん」と呼ばれるくらいにはフェミニンだったのもあり、わたしの性自認や性的指向を“心配”していた人たちからすれば、「やっと“男の子らしく”なった」と思えたのだろう。まるで『ドラゴンボール』は“普通の男の子”として見てもらえる切符のようなものだった。実際にそれまでは女の子の友達ばかりだったわたしも、『ドラゴンボール』を通して学年のやんちゃな男の子たちと仲良くなり、彼らと『ドラゴンボールグッズ』を見せ合ったり、交換したりして遊ぶようになっていた。それは、誰もわたしを“変な子”として見ないと初めて感じた瞬間でもあり、わたしはその環境に居心地の良さを感じていた。『ドラゴンボール』はわたしに、現実世界に安心できる場所を与えてくれたのだ。
自身の性のあり方への葛藤と変化とともに変わっていった『ドラゴンボール』との関係性
しかし、歳を重ねるにつれ、わたしの興味も移り変わり、11歳の頃に『ディズニーチャンネル』で観た『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』に魅了されて以降、わたしのクィアネスは加速した。ハンナ・モンタナを演じるマイリー・サイラスを好きになったことをきっかけに、海外のアーティストやドラマに夢中になっていくのと同時に、「自分らしさ」を表現する人や作品にエンパワーメントされていったのだ。海外の作品を観ていたり、アーティストの言動を追っていると、性的マイノリティに対して力強く、心強いメッセージを受け取ることができ、今までそんな作品や人と出会ったことはなかったわたしにとっては、初めて自分が自分でいることを他者から肯定された気持ちだった。これまでは親や周囲を安心させるためにあらゆる物事を選んできた人生だったが、この時から「わたしが心から好きだと言えるのはどんなものなのか」、「何から勇気や希望、夢をもらっているのか」を考えるようになっていったのだ。
そのぐらいから、わたしと『ドラゴンボール』は距離ができ、いつしか祖母に買ってもらった漫画やコツコツと集めていったグッズたちは思い出の品としてダンボールにしまわれ、押入れの中で眠りについた。その間わたしは、映画や音楽、ドラマなど、国内外問わずいろんなコンテンツを楽しみ、クィアやフェミニズムに関する表象を積極的にインプットし、今のコンテンツクリエイター(主にメディアや広告の編集、執筆、撮影)としての仕事でアウトプットしている。もちろんわたしはクィアやフェミニズムコンテンツが大好きだし、エンパワーメントされているし、今の社会に必要なものだと思っている。それはわたし自身が、シスゲイ男性からノンバイナリーにトランスし、今もなお別のアイデンティティにトランスしている過程のなかで、そうしたコンテンツに救われている/救われてきたということが大きいからだと思う。親や周囲の人にわたしの性のあり方を常にオープンにしている今でさえ、この社会でトランスジェンダーとして生きていくことを、心から幸せと感じたり、自分自身を肯定することは正直むずかしい。だからこそ今もなお社会から蔑ろにされている人たちの現在や未来を描くコンテンツを、これからも必要なものとして取り入れたり、作り続けていくだろう。
インナーチャイルドを抱きしめるための再会
同時に、純粋にラブロマンス作品やコメディ作品、アクション作品なんかをしばらく楽しめなくなっている自分がいるなと最近になって思うようになってきた。それは、そういったジャンルの作品はこれまで、特定のアイデンティティを持つ人を、いないものとして扱ってきたり、笑いの対象として扱ってきた歴史があるということも間違いなくある。また『ドラゴンボール』といった、いわゆる“男の子が好きな作品”をトランスしたわたしが好むことによって、「結局男っぽいじゃん」と思われることに対して強い抵抗感があったからこそ、少年漫画原作の作品や、アクション作品に対して距離ができていったようにも思う。しかし、そうなるとわたしのインナーチャイルドはいつまで経っても、自分が好きなものを選べずに、周囲に合わせた選択を取っていた苦しい時間を過ごし続けることになる。大人になったわたしが、わたし自身の性のあり方をある程度受け入れられた今、自分の選択として、幼少期に選択できなかったものを選択し、選択させられたと感じるものを自分が選択し直すことで、わたしの心の奥でしゃがみこんでいるインナーチャイルドを癒してあげられるんじゃないかと思うようになった。
そんな仮説を自分のなかで立て、昨年から幼少期に好きだったもの、きっと好きだったけど選択できなかったものをわたしの家に迎え入れてみた。横目で観ていた『ラブ☆コン』の漫画、本当は小栗旬や生田斗真が好きだったのに、自分の性的指向がバレないように堀北真希が好きだと嘘をついて観ていた『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のDVDボックス、フェミニンな下着、ラインストーンがついたヤンチャな帽子……。その1つとして実家の押入れに眠っていた『ドラゴンボール』の漫画を読み返し、距離ができていた間に地上波で放送されていた『ドラゴンボール超』全131話を観てみると、当時は親や周囲が安心するからと選んだこの作品も、しっかりわたしは大好きだったのだ。あの時、『ドラゴンボール』に夢中になっていたわたしは存在したし、わたしが夢中になる世界もそこにはあった。亀仙人やウーロンによるセクハラを容認せず、常に強く自分を持つブルマをはじめとする女性たち、国や星の違いを差別することなく仲間になっていく悟空、女性のメインキャラクターとしてはじめて悟空とともに闘いの旅へと出るパン、ジェンダーニュートラルな容姿や話し方をするキャラクターたち(特にフリーザ)、近未来を感じさせるメカの数々……。わたしはそんな『ドラゴンボール』の世界に、当時も今も魅了されている。
長い間、『ドラゴンボール』と距離ができていたが、昨年より再び関係性ができ、今のわたしも、インナーチャイルドも心から喜んでいる。まるで、同窓会で久しぶりに再会した親友と、また頻繁に遊ぶようになったみたいな気分だ。これによって、わたしのインナーチャイルドが持つ傷を全て癒せたわけではないが、「わたしは何が好きなのか」を改めて考える大きなきっかけになったことには違いない。
これからも続く、摩訶不思議アドベンチャー
今年の秋から放送予定の『ドラゴンボールDAIMA』も待ち遠しく思っていた、そんな矢先に作家の鳥山明氏の訃報が発表された。もちろん、鳥山氏とは一度も会ったことがなければ、顔さえもニュースで報道されるまでは知らず、ずっとジャージを着たロボットのイメージしかなかったから、なぜ自分がこんなにも悲しんでいるのか正直わからなくなる瞬間もあった。しかしわたしたちは、たとえ彼と会ったことがなくても、彼が「ワクワクすっぞ」と思い描いた景色やメッセージ、ストーリーを常に受け取っていたのだ。それは彼と会話をしてきたことのように思えるし、間違いなくわたしたちと鳥山氏のなかにも特別な関係性が築かれていたように思う。わたしたちのなかから『ドラゴンボール』との思い出が消えない限り、『ドラゴンボール』も鳥山氏も永遠に生き続けるとわたしは信じている。それに、鳥山氏が描いてきた「あの世の世界」はいつでも陽気で楽しそうだった。きっと今頃は『あの世一武道会(『ドラゴンボールZ』に出てくる、死後の世界で行われる武道大会)』の開催に、鳥山氏も心踊らせていることだろう。
今後も、いろんなかたちで『ドラゴンボール』は続いていくだろうし、何度だってこれまでの伝説を振り返るだろう。これからの『ドラゴンボール』シリーズがどんな風に進んでいくのか、わたしのこれからの人生のなかでどんな関わりを持っていくのか、わたしと『ドラゴンボール』の摩訶不思議アドベンチャーはこれからも続いていく。

著者プロフィール:中里虎鉄
1996年、東京都生まれ。編集者・フォトグラファー・ライターと肩書きに捉われず多岐にわたり活動している。雑誌『IWAKAN』を創刊し、独立後あらゆるメディアのコンテンツ制作に携わりながら、ノンバイナリーであることをオープンにし、性的マイノリティ関連のコンテンツ監修なども行う。
Instagram:@kotetsunakazato
LATEST STORIES

兄弟時代の名作、キリンジ サード・アルバム『3』スペシャル特典付きLP&カセットが本日2/25発売!! 併せて 「エイリアンズ」「Drifter」他ワーナー時代の名曲MV11曲が4KデジタルリマスターでYouTubeアップグレード公開開始!!!

刀剣乱舞、ついに“氷上の本丸”を開帳。初のアイスショー『刀剣乱舞 – ICE BLADE -』2026年10月、国立代々木競技場にて開催決定!──刃(やいば)が描く軌跡は、銀盤へ。刀剣男士の新たな戦いが幕を開ける。